目次
このブログでまとめを始めたスプリンターの半月板断裂日記、2回目は【整形外科受診後〜15日】を題材にまとめていきます。
〜5日
トレーニング中に痛みが出て2日後に整形外科を受診、外側半月板損傷の診断、保存療法を開始しました。
とは言っても、安静にしていても何も変わりません。
ヒアルロン酸注射は次の日から大きく効果が出始め、腫れはありながらもハーフSQの肢位まで曲げられるようになりました。(この時点ではハーフSQまでの屈伸が許可されていた。)
しかし膝の運動をするには程遠いため、「消極的」と「積極的」にリハビリを分けて実践しました。
消極的リハビリ
- マイクロカレントの常時活用(24h→就寝時のみ)
- 移動時のサポーター着用
- ロキソニンの服用
最も注意しなければならないのは「症状の悪化」です。
積極的リハビリを行いたいところですが、まずは安静を優先にしつつ、痛み無く生活を送れるように計画を組みました。
治癒促進のためにマイクロカレントを常時使、パッドの痒みもあるため、徐々に着用時間を減らしました。
そして、仕事や移動に支障があるため、サポーターと渋々痛み止めは活用しました。(湿布は一切使いませんでした)
積極的リハビリ
- 患部外マッサージ
- 浴槽内での可動域訓練
- 上半身トレーニング
浴槽内で体を温めながら関節運動を行い、少しずつ可動域を広げることから始めました。
その後、殿部や大腿部を中心にマッサージガンやローラーを活用して、ストレッチができない分、ほぐすことに重点を置きました。
入浴後だけで無く、時間がある時は、膝が硬まらないようにほぐす機会を増やしていました。
可動域が小さくなったことでストレッチができず、膝周りがスッキリしなかった事を覚えています。
伸ばすことで動きが改善しそうな感覚はありましたが、無理はできないため断念しました。

膝以外は特に問題無く動けるため、ケアと並行しながら上半身のトレーニングは積極的に取り組みました。
普段時間を割くことが少ない上半身のトレーニング、筋肥大を目的としてセットを組みました。

目立った症状
- 可動域制限
- 角度による膝崩れ
- 冷えによる痛み
痛み自体は徐々に和らいでいますが、可動域制限が影響して様々な不調を起こしていました。
冬場ということもあり、冷えることで可動域が更に狭くなり、膝の痛みと歩きにくさに苦しみました。
最も怖かったのは「膝崩れ」、少し体重のかけ方を変えるだけで倒れそうになるため、ベッドの縁やスロープに捕まりながら歩くことよくありました。
〜10日
可動域自体は改善傾向にあり、屈伸運動もスムーズになってきました。
痛くてしゃがめないと言うより、膝関節に何かが挟まるような感覚があり、完全に屈伸をすることは困難です。
- 就寝時マイクロカレント
- 入浴後・リハビリ前のセルフマッサージ(範囲を広げて実施)
- 上半身トレーニング
- 浴槽内可動域訓練
上記4点を継続しながら、新たな取り組みを開始しました。
- 殿部の負荷トレーニング
膝をケガした根本を考えた時に、「右殿部の弱さ」が大きく関係していると思いました。
思い返すと、スクワットや動きづくりをした時に、右脚の不安定感があった気がします。
この段階では直接的に原因を探ることはしませんでしたが、可能性の一つとして、膝の負担を減らすために負荷をかけ始めました。
- 日中の貼るカイロ活用
時期は年末年始、特に脚の冷えが起きやすいため、気づかない間に膝の動きが硬くなります。
そこでサポーターと並行して貼るカイロを使用して、常に膝が冷えないように策を打ちました。
これが意外と効果的であり、活動中の痛みが軽減されました。
治癒促進のマイクロカレントよりも、痛みの軽減を目的とした貼るカイロを優先して活用するようになりました。
- 有酸素運動の開始
受傷後8日目辺りから、サポーター着用での歩行に不自由を感じるようになってきました。
具体的には、膝の伸展が矯正されるため、前方へ倒れそうになる事が増えました。
階段昇降も容易となり、長時間の歩行や砂利道などを避ければ、サポーター無しでも痛み無く歩けるように。
そこで大きな賭けになりましたが、トレッドミルでのウォーキングを開始しました。
筋温と可動域の獲得を行ってから、20分を目標に歩きます。
有酸素運動を始めた理由は、「循環改善による血流増加」です。
時速4kh、歩くとしては正常スピードくらいですが、手すりを掴まないと不安定な歩行となっていました。
ここで意外だったのは、主観と客観で大きなズレがあったことです。
私の感覚としては少し歩きにくい程度でしたが、動画を見ると明らかに右の振り出しができていませんでした。
少し無理をしている自覚はありましたが、この日を境に有酸素運動をリハビリに取り入れ始めました。
目立った症状
- 冷えによる患部の痛み
- 運動時の不安定感/膝内の挟み込み
痛み自体は緩和されてきましたが、寒さが膝の負担となりました。
冷え硬まることで運動の不安定感や屈伸運動の障害となり、痛みが出ると1日中鎮痛剤を使いながら生活するレベルでした。
反対に、膝を温めたり動きづくりをしっかり行うことで、運動制限は緩和されやすくなってきました。
ここで問題となったのは【膝内の挟み込み】、想像になりますが、半月板が挟まっているような感覚が強く出るようになりました。
歩行以外に挟み込みが気になったのは「靴下を履くとき」や「床の物を拾うとき」、ある角度まで曲げると膝の中が引っかかりが起こりました。
些細なことですが、日常生活のあらゆる事でストレスを感じることが増えました。
〜15日
10日目に有酸素運動を取り入れた結果どうだったのか?
結論、次の日に痛みは気にならず、日常生活をする分には特に問題は起こりませんでした。
そのため、ここからは積極的に有酸素運動(トレッドミルでのウォーキング)を取り入れる様になりました。
無理はしないことは前提として、
- 下肢の刺激入れ
- 患部外トレーニング
- 患部外マッサージ
- 浴槽内可動域訓練
などを組み合わせながら、できるだけ動くことに重点を起きました。
さらに進歩があったのは、【ハムストリングスのストレッチ】ができるようになったことです。
入浴後に全身をほぐしてから少しだけ伸張ストレスをかけたところ、膝の痛みを起こさずに伸ばせました。
ハムの硬さが動きの制限をかけていたので、少しだけですが楽になりました。(左脚と比較すると全然ストレッチはできていません)
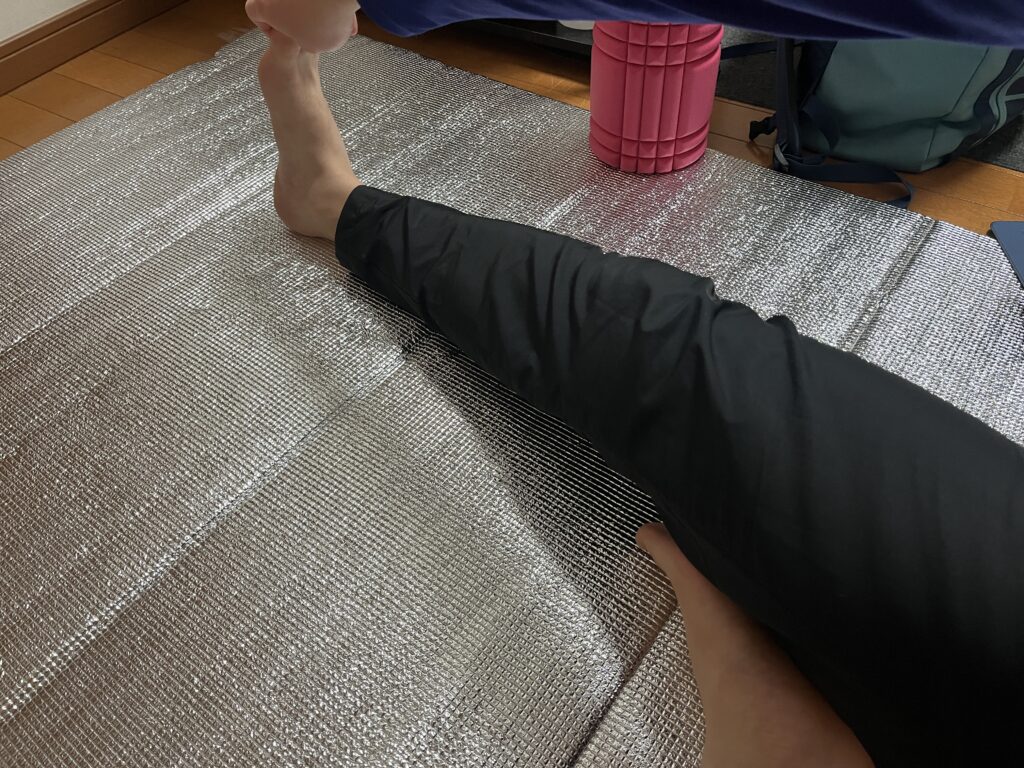
そして初診から2週間が経ち、ドクターの診察と2回目のヒアルロン酸注射へ行ってきました。
ここでネックとなったのは、ヒアルロン酸注射を打った後はリハビリができなくなることでした。
向かって左側が注射を打った右膝、膝蓋骨の輪郭が分かりにくい程に腫れが起きています。
打った直後は膝が曲がりにくくなり、注射針の入った部位の痛みが強く出ます。

また、ヒアルロン酸注射を打った後は吸収が早まらないように
- 当日の入浴禁止(シャワーのみ)
- 運動禁止(血流増加が起こるため)
などの制限がかかります。
リハビリを行いたい気持ちを抑えながら、大人しく体を休めます。
2日くらい経つと痛みも落ち着き、動きにも改善が見られました。
捻りによる痛みは残りますが、アップを行えば小走り程度ならできるようになっていました。
ドクターの見解
状態としては経過良好でしたが、【保存療法による経過観察】、引き続き【運動中止】、2週間後に再診となりました。
まだ受傷から日が経っていないため、焦っても仕方ないのは分かっていました。
しかし、実際に体の状態を聞かされると、少しだけですが気持ちに焦りが出てきました。
心では分かっていても、どこか落ち着かない。
この気持ちが後々、リハビリ生活に追い打ちをかけることとなりました。
走れなくなってから2週間が経過して
最初は走れなくなったことを受け止め、前向きにリハビリを行う気持ちでいました。
症状も徐々に改善傾向にあったため、3ヶ月程度の安静で走れるように戻ると思っていました。
2週間が経過して、走れないことが現実味を帯び始め、気持ちが落ち込むことが増えた気がします。
そこまで悲観したわけではありませんでしたが、シーズンインに間に合うのか?今後同じパフォーマンスを発揮できるのか?など、考え出すと不安になることが浮かんできます。
それでも、できることに全力を注ぐ以外に方法はありません。
次のブログでは、更に追い込みを始めたリハビリの内容や、受傷から1ヶ月が経って起こした行動についてまとめていきます。
リハビリ・手術の時系列
受傷直後:スプリンターが半月板断裂を起こした話
整形外科受診後〜15日:本ブログ
16日〜30日:半月板断裂 積極的リハビリと精密検査の決断
31日〜41日:半月板断裂と円板状半月板
42日〜61日:半月板断裂 思い切って攻めたリハビリを行う
セカンドオピニオン/手術前リハビリ:半月板断裂 セカンドオピニオンと手術前リハビリ
手術前の準備/不安だったこと:半月板断裂 手術前の準備 不安だったこと
入院/手術の話 手術後のリハビリ:半月板断裂 入院/手術の話 手術後のリハビリ
手術後1ヶ月:半月板断裂 手術後1ヶ月間のリハビリ
手術後1ヶ月②:半月板断裂 手術後1ヶ月間のリハビリ②
手術後のアイシング−考察:膝手術後の腫れとアイシングの考察
アスレティックリハビリテーション:スプリント動作を再獲得するためのリハビリ






コメント